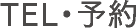50歳以上の方のベッドの寝返り困難な症状を特徴とする【リウマチ性多発筋痛症】①
2015年07月17日 リウマチ性疾患
リウマチ性多発筋痛症 【概要】 リウマチ性多発筋痛症(polymyalgia rheumatica; PMR)は、50歳以上の年齢の方に多く発症し、肩の痛み、体に近い側の肩や上腕、大腿などの四肢近位筋主体の痛みや朝のこわばりと、微熱、倦怠感を呈する炎症性疾患です。
【頻度】
男女比は1:2から1:3で女性に多く、発症年齢のピークは70-80歳とされていますが、病因は現在のところ不明です。
<巨細胞性動脈炎の合併>
日本では少ないですが、欧米ではリウマチ性多発筋痛症の5-30%に巨細胞性動脈炎(側頭動脈炎)を、また逆に巨細胞性動脈炎の約半分にリウマチ性多発筋痛症を合併し、共通の病因が考えられています。リウマチ性多発筋痛症と巨細胞性動脈炎はともにHLA-DR4という遺伝子の或る特殊な型が関係していると言われています。また、発症や病状に季節変動が示唆されており、感染症などの環境要因が病気のきっかけを作るのではと言われていますが、明確な病因は不明です。
【症状】
肩の痛みが最も頻度が多く(70-95%)、次いで頚部・臀部の痛み(50-70%)、大腿の疼痛、こわばり感を認めます。症状は一般的に左右対称に出現し、特に腕を挙げたり、起き上がるなど、動作時に強くなる痛みが特徴的です。典型的には、ベッドの寝返りがきつい・できないといった症状を訴えます。筋肉には圧痛がありますが、病気そのものによる筋力低下や筋の萎縮はありません。発症は比較的急速で、数日から数週間のうちに症状が出現し、持続します。
こわばりは、すべての患者さんで認め、肩や臀部、大腿などに起床後最低30分は持続します。
多くの場合、このこわばりは体を動かさずにじっとしていると強くなります。
また、発熱、食欲不振、体重減少、倦怠感、うつ症状などを伴うこともあります。
関節リウマチとは異なり、激しい関節痛や骨の破壊はまれなものの、約半数に膝や手の関節の腫れや痛みを伴う場合もあります。但し、関節よりも筋肉の症状が強いのが特徴です。また、手や足の甲、手首や足首に、押すとくぼんだままの圧痕が残るようなむくみを伴うこともあります。リウマチ性多発筋痛症の10-15%に手根管症候群を伴うことがあります。
最も典型的には、高齢者の方が、「ある日急に両腕が肩より上に挙げられなくなって、両肩から二の腕にかけてと太ももに筋肉痛がでてきた。症状は続き、特に朝に顕著なこわばりが出るようになって、着替えがしにくかったり、寝返りしにくいなど、体が動かしにくくなった」というようなものです。
なお、こめかみ周囲の頭痛、噛む時のあごの違和感、視力障害、38℃以上の発熱を伴っていれば巨細胞性血管炎の合併も疑われますので、より詳細な検査が必要です。
【診断】
この病気を診断する上で大切なことは、まず症状からこの病気を疑うことです。また、関節リウマチや、他の膠原病や感染症、がんによる症状をこの病気と誤認しないことも大切です。この病気の診断をするために、いくつかの診断基準が存在し、そのうちよく使われるものの一つが以下に挙げるBird(バード)の診断基準です。
Bird(バード)の診断基準(1979年)
1.両側の肩の痛み、またはこわばり感
2.発症2週間以内に症状が完成する
3.発症後初めての赤沈値が40 mm/h以上
4.1時間以上続く朝のこわばり
5.65歳以上発症
6.抑うつ症状もしくは体重減少
7.両側上腕の筋の圧痛
上記7項目のうち3項目を満たすもの、もしくは1項目以上を満たし臨床的あるいは病理的に側頭動脈炎を認めるものをリウマチ性多発筋痛症とみなします。治療薬のステロイドが著効した場合、その診断はより確実になります。
検査所見としては、血液検査でCRPや赤沈といった炎症反応を示す値の上昇を認めます。他の筋肉痛を来たすような膠原病で実際に筋肉の炎症が起きるような皮膚筋炎/多発性筋炎とは違って、筋酵素(CK)の上昇は認めません。特別な「この検査が陽性であればリウマチ性多発筋痛症が確定です」と言えるような検査はありません。関節リウマチでみられるリウマトイド因子や抗CCP抗体、膠原病でみられる抗核抗体やその他の自己抗体が陽性となることは少ないです。そのため、診断基準を参考にしながら、血液検査結果や身体所見、プレドニゾロンによる治療の反応性などから総合的に診断することになります。プレドニゾロン治療による改善が乏しい場合は巨細胞性血管炎の合併など、他の病気の可能性も検討することが必要です。
【治療】
<初回治療>
これまでの経験的な知見からステロイドが著効することが知られています。症状の重症度、体重、合併症(糖尿病、高血圧、骨粗鬆症、緑内障などステロイドで悪化する病気を有しているか)などを考慮し、ステロイドの初回投与量を決定します。多くの場合、10~20 mg/日のプレドニゾロンといった、少量のステロイド内服が使用されます。側頭動脈炎を合併した場合は中等量~大量(30~60mg/日程度)のステロイドが必要となります。
基本的にはほとんどの方が少量ステロイドを内服し始めると速やかに反応し、数時間から数日で痛みやこわばりが大幅に改善します(3日以内に50~70%の改善)。もし治療開始後1週間以内に症状が改善しない場合は、プレドニゾロンを5~10 mg/日程度増量します。約1週毎に効果を見極め、不十分であれば更に5~10 mg/日程度毎、最大30 mg/日程度まで増量します。
ステロイドの朝1回内服で夕方や夜に症状が強くなる場合は、朝夕2回や毎食後の3回に分割するとステロイド同量のまま症状が軽快することがあります。その後、臨床症状や検査データを見ながら、ステロイドを減量していくことになります。経過によって異なりますが、減量の例として、初回プレドニゾロン量が15mg/日の場合、2~3週間初回量を用いた後、12.5mg/日を2~3週、次に10mg/日を4~6週、それ以降は4~8週毎に1mg/日ずつ減量するような形になります。最終的に早くて約1年でステロイドを中止できる人もいますが、症状の再発により少量のステロイドを内服し続ける必要のある方が多いです。現在、初回治療でステロイドと同等の有効性が証明されている薬剤はありません。
<再発時の治療>
痛みや朝のこわばりが再び出現した場合、再発を考えます。再発は25~50%の割合で起こると言われており、特にステロイドを早く減量している過程や既に中止した際に起こりやすいです。再発時の最適な治療法は確立していませんが、経験的に以下の通りに治療する場合が多いです。ステロイド減量で再発した場合、症状なくコントロールされていた減量直前のステロイド量に戻します。
<その他の治療>
痛み止めとして非ステロイド性抗炎症薬(NSAID)が用いられることがありますが、ステロイドと併用すると、NSAID単独で使用するときよりも高率に消化管の潰瘍が生じることが分かっており、注意が必要です。使用する場合はプロトンポンプ阻害薬や粘膜保護剤も一緒に用いることが推奨されます。
【生活上の注意】
巨細胞性動脈炎の合併が無ければ基本的には治療後の見通し(予後)は良好で、関節リウマチのように関節破壊を来たすことはなく、臓器障害を来たすこともありません。数か月から数年で病気の勢いが収束し、ステロイド治療が最終的に中止可能なこともあります。多くの例で2~3年は薬物治療を要します。プレドニゾロン5 mg/日以下が長期にわたって必要になる患者さんもいます。また、一連の初回治療終了後10年以内に約10%の患者さんが再発すると言われています。
病気そのものによって死亡率は高まりませんが、ステロイドによる副作用(感染症、糖尿病、高血圧、脂質異常症、骨粗鬆症、緑内障、白内障、筋量低下など)の影響を最小限にする配慮が必要です。また、経過中に巨細胞性動脈炎の合併がないかを注意深く観察する必要もあります。ステロイドによる副作用には注意が必要ですが、病気そのもののために特別に気をつけることはありません。